耐震診断とは?種類や流れを解説
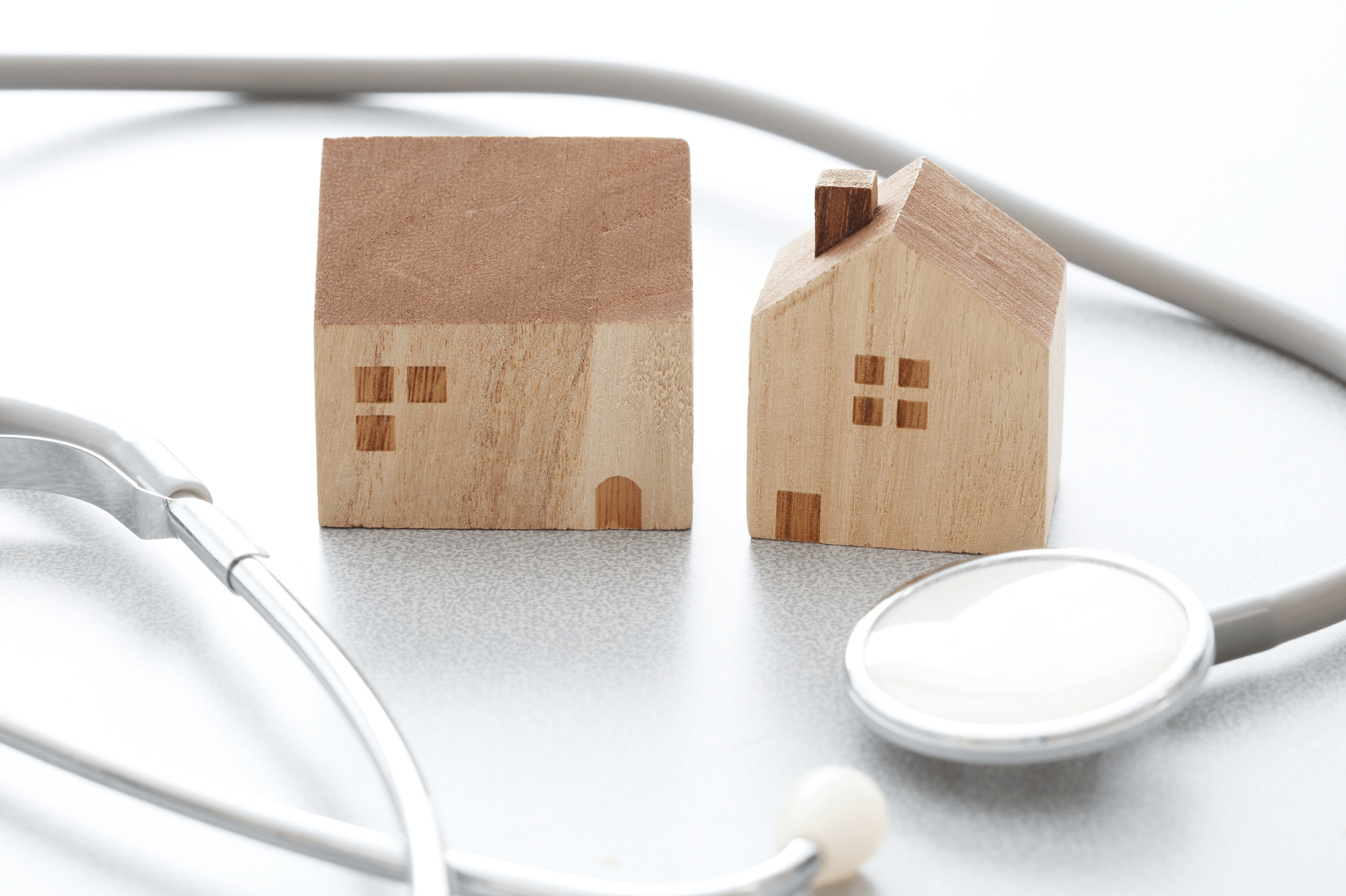
建物を所有している人の中には、大地震が発生したときに建物が倒壊せず、人命を守れるだけの耐震性を有しているかを確認したい方も多くいます。
地震大国である日本では、自身や周囲の人の身を守るためにも、耐震診断を通して建物の耐震性(強度)を確認し、必要な補強工事を計画・実施することが重要です。
では、耐震診断は、どのような内容を診断し、どのように進められていくのでしょうか。
この記事で解説します。
1. 耐震診断とは
耐震診断とは、建物に必要な耐力として、建築基準法で定められている値と、現状の値を比較し、建物の耐震性能を評価・判定することです。
構造部材の強度や変形能力(粘り強さ)、老朽度、建物の形状等が診断の中心項目となります。
建築基準法は1950年に制定されて以降、耐震性に関して2度の大きな改正が行われました。
1度目は、1968年の十勝沖地震の被害を受けて、1971年に主に鉄筋コンクリート造の柱のせん断設計法が変更され、2度目は、1978年の宮城県沖地震の被害を受けて、1981年に耐震基準が大幅に改正されています。
これにより1981年6月1日以降に新たな基準で建築確認※を受けた建物を「新耐震建物」、それ以前の基準で建築確認を受けた建物を「旧耐震建物」と呼ぶことが一般的です。
※建築確認・・・・着工前に行う図面審査
新耐震建物は、人命保護の強化のため建物の倒壊リスクを大幅に減少させることを主眼として震度6強の大地震に耐えられるように設計されており、旧耐震の物件よりも大幅に強度が向上しています。一方、旧耐震建物は、震度5程度までの中規模な地震に耐えられるように設計されているため、震度5強よりも大きな地震に遭遇すると、致命的な損傷を受けるリスクがあります。旧耐震建物はもとより新耐震建物においても劣化により耐震性能が不足している場合は、耐震診断を行い、耐震性を評価するとともに耐震補強などの対策を検討することが重要です。
2. 構造別の耐震診断
耐震診断には、建物の構造によって以下のような方法があります。
この章では、構造別の耐震診断について解説します。
2-1.木造および鉄骨造の耐震診断
木造の耐震診断は、簡易診断と一般診断、精密診断に大別されます。
鉄骨造の耐震診断は、一般診断と精密診断の2種類がありますが、接合部の溶接状態など詳細な調査を要するため、基本的には精密診断を実施します。
簡易診断とは、一般住宅の診断であり、耐震診断問診表によって評点を合計していきます。
耐震診断を啓発する目的もあり、一般の人でも簡単に診断できる仕様となっています。
一般診断とは、耐震診断資格を保有する建築士が行う診断であり、壁の仕様や柱頭・柱脚接合部の仕様および劣化等を非破壊で行う診断方法です。
精密診断とは、耐震診断資格を保有する建築士が行う診断であり、内装材の引き剥がし等、建物の一部を破壊し、保有水平耐力等の専門的な計算が行われる診断方法です。
耐震補強の必要性が高い建物において、より正確に診断を行うことを目的としています。
2-2.鉄筋コンクリート造および鉄骨鉄筋コンクリート造の耐震診断
鉄筋コンクリート造(RC造)および鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)の耐震診断は、第1次診断と第2次診断、第3次診断の3つに大別されます。いずれも耐震診断資格を保有する建築士が診断します。
第1次診断とは、各階の柱や壁のコンクリートの断面積と、その階が支えている建物重量から計算する簡易な診断方法のことです。
壁の多い建物には第1次診断が適していますが、壁の少ない建物では耐力が過少に評価される傾向があります。
第1次診断の結果をもって適切な補強設計を行うことは困難であり、耐震補強工事を検討している場合や、より精度の高い結果を求める場合は、一般的に第2次診断から行います。
第2次診断とは、各階の柱や壁のコンクリートの断面積と鉄筋の配置から、各部材の強度と粘り強さを計算し、各階で必要な耐力と比較する診断方法のことです。
築年の経過した建物や4~5階程度の比較的低層な建物では、最も多く行われている方法です。
第3次診断とは、柱や壁に加えて、梁(柱と柱を繋ぐ横架材)も考慮して建物の耐力を計算し、各階で必要な耐力と比較する診断方法のことです。
第3次診断は、高層建築や特殊な構造の建物で行われる方法で、第2次診断よりも精度が高いとされています。
3. 構造耐震指標(IS値)
耐震診断の結果は、IS値と呼ばれる構造耐震指標で表されます。
IS値とは、地震力に対する建物の強度と粘り強さ(靱性)を考慮し、建物の階ごとに算出された数値のことです。
IS値は、震度6~7程度の規模の地震に対する評価が下表のように定められています。
| IS値 | 評価 |
|---|---|
| 0.6以上 | 倒壊または崩壊する危険性が低い |
| 0.3以上0.6未満 | 倒壊または崩壊する危険性がある |
| 0.3未満 | 倒壊または崩壊する危険性が高い |
新耐震基準の建物は、震度6強の地震が起こってもほとんど倒壊しないよう設計されます。
IS値が0.6以上あれば新耐震基準並みの耐震性を有している建物とみなされます。
4. 耐震診断の流れ
耐震診断では、まず耐震診断資格を保有する建築士が予備調査によって建物の概要や状態、設計図書の有無等を把握し、診断レベルを設定します。
診断レベルの設定とは、例えば鉄筋コンクリート(RC)造であれば第1次診断、第2次診断、第3次診断のうち、目的に応じた診断レベルを設定することです。
診断レベルを設定後、簡易診断以外の場合は見積もりをとり、双方が合意できた段階で耐震診断がスタートします。
耐震診断の結果、耐震性の不足が判明した場合は耐震補強工事の設計を依頼し、必要に応じて耐震改修工事を実施します。
5. 特定建築物の耐震診断
特定建築物の所有者は、耐震改修促進法(建築物の耐震改修の促進に関する法律)により、耐震診断を実施し、必要に応じて耐震改修に努めなければならないとされています。
耐震改修促進法の特定建築物とは、不特定多数の人が利用する建物や、自力で避難が困難な人の利用が想定される建物のうち、以下のような大規模な建物が該当します。
【耐震改修促進法の特定建築物】
| No. | 建物 |
|---|---|
| 1 | 学校、体育館、病院、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、老人ホームその他多数の者が利用する建築物で一定規模以上の建物 |
| 2 | 火薬類、石油類、その他政令で定める危険物で規定数量以上のものの貯蔵場または処理場の用途に供する建物 |
| 3 | 地震によって倒壊した場合に、その敷地に接する道路の進行を妨げ、多数の者の円滑な非難を困難なものにする恐れのあるものとして政令で定めるもので都道府県の耐震改修促進計画に記載された道路に接する建物 |
| 4 | 3階で1,000平米以上の建物 |
東京都では、上表No.3の対象として、緊急輸送道路沿いにある一定要件※を満たす建物に対して耐震診断を義務付けています。
※建物の高さが前面道路幅員の2分の1を超える場合
緊急輸送道路とは、震災時に避難や救急・消火活動、緊急物資輸送の大動脈となる幹線道路のことであり、例えば都道の外堀通りが緊急輸送道路に該当します。
その他の自治体でも同様に、それぞれ緊急輸送道路沿いの建物に対する耐震化を求めています。
近年では、多くの自治体が耐震診断や耐震改修に関する補助金制度を設けていますので、ご確認のうえご活用ください。
まとめ
以上、耐震診断について解説してきました。
耐震診断とは、主に1981年5月31日以前の基準で建築確認を受けた建物の耐震性を評価・判定することです。
耐震診断を行い建物の耐震性を把握することで必要な補強工事の計画を立てることができ、適切に対応すれば大地震が発生した際の被害を最小限に抑えることにつながります。
自治体によっては、一定の要件を満たす建物で耐震診断が義務付けられています。
補助金制度も上手に利用しながら、ぜひ耐震診断を実施してみてください。
竹内英二
不動産鑑定士・中小企業診断士
不動産鑑定事務所である株式会社グロープロフィットの代表取締役。不動産鑑定士、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、住宅ローンアドバイザー、公認不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士)、中小企業診断士。土地活用と賃貸借の分野が得意。
- お問い合わせ・ご相談はこちら
-
03-3501-6173
[ 受付時間 ]8:50~17:00
(土・日・祝日・年末年始・夏季休暇を除く)



